一瞬にして総体を見る。
これ、壮眼の極意なり。
SENIOR GLASSES(シニアグラス)のコピー。
こちらのページに広告画像があります→コレクシオン開高健
ホーム > アーカイブ > 2009/10
一時間、幸わせになりたかったら
酒を飲みなさい。
三日間、幸わせになりたかったら
結婚しなさい。
八日間、幸わせになりたかったら
豚を殺して食べなさい。
永遠に、幸わせになりたかったら
釣りを覚えなさい。
—中国古諺—
いつか雨の日に一九世紀末のイギリス人の釣師の書いたものを読んでいるうちに中国古諺を一つ教えられた。
出典が書いてないので、どこから引用したものか、いまだにわからないでいる。
しかし、それは男による、男のための、男の諺なのである。いまこの人ごみのなかで、それがありありと昏迷のなかによみがえってくる。
この広場では、私は《見る》ことだけを強制された。
私は軍用トラックのかげに佇む安全な第三者であった。
機械のごとく憲兵たちは並び、膝を折り、引金をひいて去った。
子供は殺されねばならないようにして殺された。
私は目撃者にすぎず、特権者であった。
私を圧倒した説明しがたいなにものかはこの儀式化された蛮行を佇んで《見る》よりほかない立場から生れたのだ。
安堵が私を粉砕したのだ。
私の感じたものが《危機》であるとすると、それは安堵から生れたのだ。
広場ではすべてが静止していた。
すべてが薄明のなかに静止し、濃縮され、運動といってはただ眼をみはって《見る》ことだけであった。
単純さに私は耐えられず、砕かれた。
誰かの味方をするには誰かを殺す覚悟をしなければならない。
何と後方の人びとは軽快に痛憤して教義や同情の言葉をいじることか。
残忍の光景ばかりが私の眼に入る。
それを残忍と感ずるのは私が当事者でないからだ。
当事者なら乗りこえられよう。
私は殺しもせず、殺されもしない。

私は虚脱してすわりこむ。
全身がふるえ、腕がふるえ、手がふるえ、ラッキー・ストライクがふるえる。
三十四時間の焦燥と緊迫と疲労は霧散した。
一滴の光が獲得できた。
瞬間は手にできた。
虚無の充実で輝きわたる。
魚を釣りたかったらコスタリカへいけ。
男になりたかったらターポンを釣るんだ、諸君。
新しい御馳走の発見は人類の幸福にとって天体の発見以上のものである。
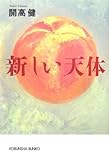


釣師の中にはせっかちで色好みのやつが多いという。
これがなぜかよくわからない。
いまの日本の "マスコミ" とはハイエナとカラスとオオカミを乱交させてつくりあげた、つかまえようのない、悪臭みなぎる下等動物である。
おためごかしの感傷的ヒューマニズムと、個性のない紙芝居じみた美意識と、火事場泥棒の醜聞あさり、ナマケモノぐらいの大脳とミミズの貪慾をかきまぜてでっちあげた、わけのわからないなにものか儲かるものである。
正体はつかめないとしても、接したらたちまち顔をぬれ雑巾で逆撫でされたような気持ちになり自殺を考えたくなる、なにものかである。
スリは孤独な芸術家である。
その芸魂は彼らの指さきの閃光に似た運動に濃縮して語られ、なんの説明もいらない。
わずらわしい知性や、くどい感性などの影響は微塵もうけぬ。
彼らは一秒に一日を賭け、いっさいから自由である。
二十世紀の生活を支配するのが "群衆のなかの孤独" という感情であるとするならば、彼こそは孤独のなかの孤独者、しかも白熱的に充実した孤独者である。
古本屋歩きは釣りに似たところがある。
ヤマメを釣ろうか、フナを釣ろうかと目的をたてることなく歩いてはいても、たいてい、一歩店のなかへ入っただけで、なんとなくピンとくるものがある。
魚のいる、いないが、なんとなくわかるのである。

昨日海を見た。
今日山を見た。
君は元気か、
ボクも元気だ。
こいつはつまり言葉なんだ。
瓶に詰められた会話なんだ。
夏の元気、
贈ります。

牛なみの力でゆっくりゆっくりと海底から円を描きつつ、走りつつ浮揚してくるこの怪物の重圧に耐えるには、私の腕と、肩と、背筋、腰筋、臀筋はあまりにも薄弱である。
一億五千年前を釣ったのだ。
気の遠くなるような時間を一瞬に私はさかのぼり、種の奔流と混沌のさなかをこえて一時代に到達したのである。
なかでも作家の故開高健さんはよく通ってくださって、今でも指定席にはプレートをつけています。
年に1回「開高記」(開高さんの命日)にはゆかりのお客さまたちが皆さんお集まりになってそれは賑やかです。
ミキシンググラスにキンキンに凍った氷を用意する。
液体を注ぐと鳴くようなその氷に、やはり冷凍庫で凍るほど冷やしたドライジンを注ぐ。
さらにベルモットを加え、ビターを一滴。
軽くバースプーンで一回だけクルリとかき回して、冷やしたカクテルグラスに注ぐ。
つまり、冷たさとスピードこそがマティーニの命。
美食とは異物との衝突から発生する愕きを愉むことである。
食べるあとあとから形も痕もなく消化されてしまっていくらでも食べられ、そして眠くならないというのがほんとの御馳走というものではあるまいか。
文学作品も、ほんとの名作というものは、読後に爽快な無か、無そのものの充実をのこし、何も批評したくなくなる。





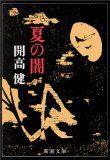




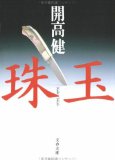


私はおしひしがれ、「人間」にも自分にも絶望をおぼえていた。
数年前にアウシュビッツ収容所の荒野の池の底に無数の白骨の破片が貝殻のように冬の陽のなかで閃いているのを見たとき以来の、短くて強力な絶望だけが体を占めていることを発見した。
あとでジャングルのなかで集結したとき、私は30名ほどの負傷兵を見た。
あたりはぼろきれと血の氾濫であった。
彼らは肩をぬかれ、腿に穴があき、鼻を削られ、尻をそがれ、顎を砕かれていた。しかし、誰一人として呻めくものもなく、悶えるものもなかった。
血の池のなかで彼らはたったり、しゃがんだりし、ただびっくりしたようにまじまじと眼をみはって木や空を眺めていた。
そしてひっそりと死んだ。
ピンに刺されたイナゴのようにひっそりと死んでいった。
いまたっていたのがふとしゃがんだなと思ったら、いつのまにか死んでいるのだった。
世にも不思議なことがある
どう考えてもわからない
四年前には75センチのイトウが二匹
それもたてつづけに釣れたのに
今日は皆目ボウズなのだ
オデコなのだ
アラスカではナクネク川の恐怖
アイスランドではラクサ川の奇跡
西ドイツではバイエルンの戦慄と呼ばれたこの私に
一匹も釣れないのだ
1000円もするヘアトニックをつけてきたのに
いったい日本はどうなるのだろうか
たどたどしい雄弁と警告、寸鉄の痛烈と正確、英知と眼力と詩情があり、 ” 真人”の風格を感じさせられる。
開高健



何かの事情があって
野外へ出られない人、
海外へいけない人、
鳥獣虫魚の話の好きな人、
人間や議論に絶望した人、
雨の日の釣師・・・
すべて
書斎にいるときの
私に似た人たちのために。
ハイネは、遊んでいるときだけ男は彼自身になれると、いった。
ニーチェは、男が熱中できるのは遊びと危機の二つだけだと、いった。

![巨人と玩具 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/21nVBVuEDoL._SL160_.jpg)

みんな、山を見る
オレ、川を見る
みんな、東京に集る
オレ、旅に出る
テレビで見る
トリス飲む
"越前"という字を見るたびに私は暗い空、暗い海、暗い雑木林を思いだす。
柔らかくて深い深雪に淡い陽が射し、雪片の燦めきとかげろうのたゆたいのなかで一点、二点、まさに灯がついたようにいきいきと、咲くというよりは閃めくようであったスイセンを思い出すのである。
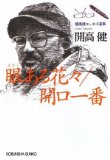
私はどんなものでも食べる。
大阪生まれのせいだろうか。
食べることには目がない。
朝、目をさまして、まず考えることは、さて今日はどんなものに出会えるだろうかということである。
あれはどうだろう、これはどうだろう、熊掌燕巣、ふとんのなかで目をパチパチさせながら想像を走らせるときの楽しさったらない。
ここ以外のところならどこへでもいきたい。
どんだけ純粋を求めても必ず別のものが入ってくる。
それが入ってくることで、強くなり豊かになれるのではないですか。
危機と遊び、男が熱中出来るのはこの二つ。

釣師をさしてホラ吹きだというよくある批評はネコをさしてニャオーといって鳴くという程度の指摘にすぎず、精神の貧困もいいところである。
よしんば釣師があきらかにホラと判別できるホラを吹いたところで、やっぱりその批評は貧困である。
いったい人間は魚を釣っているのであるか。
それとも魚に釣られているのであろうか。
遊びを追っていくと、きっと、どこかで、底なしの穴を覗かせられる。

「人間」らしく
やりたいナ
トリスを飲んで
「人間」らしく
やりたいナ
「人間」なんだからナ
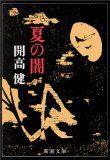
最初の一匹はいつもこうなんだ。
大小かまわずふるえがでるんだよ。
釣りは最初の一匹さ。
それにすべてがある。
小説家とおなじでね。
処女作ですよ。
だからおれは満足できた。
もういいんだ。
魚は逃がしてやりなさい。
おれたちは遊んでるんだ。
入ってきて、人生と叫び、出ていって、死と叫ぶ。

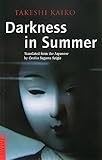
残るもの
小さくなりぬ
秋の風
開高健
跳びながら一歩ずつ歩く。
火でありながら灰を生まない。
時間を失うことで時間を見出す。
死して生き、花にして種子。
酔わせつつ醒めさせる。
傑作の資格。
この一瓶。


